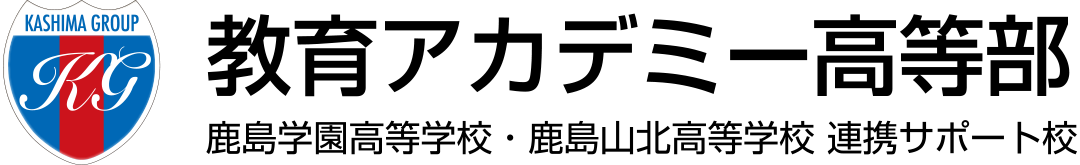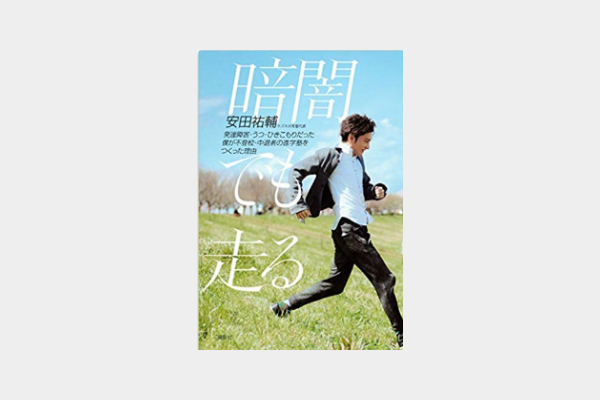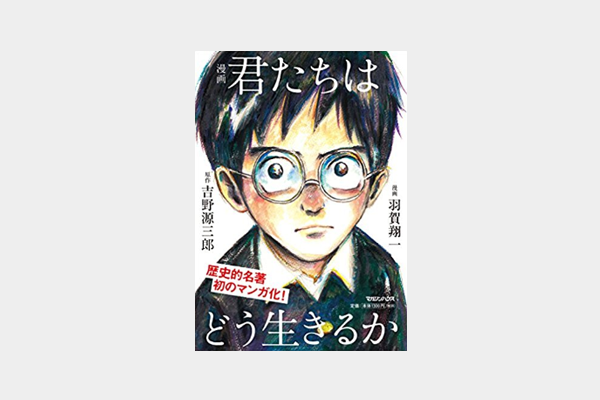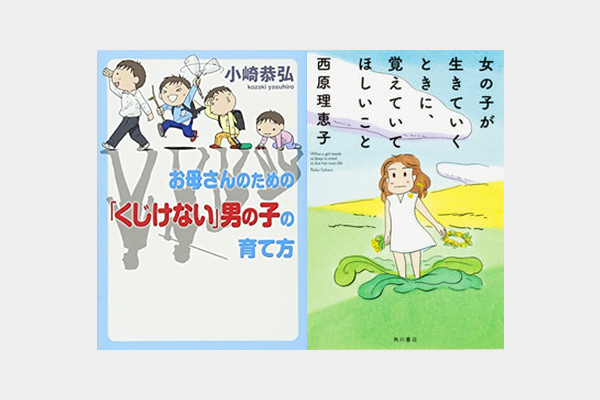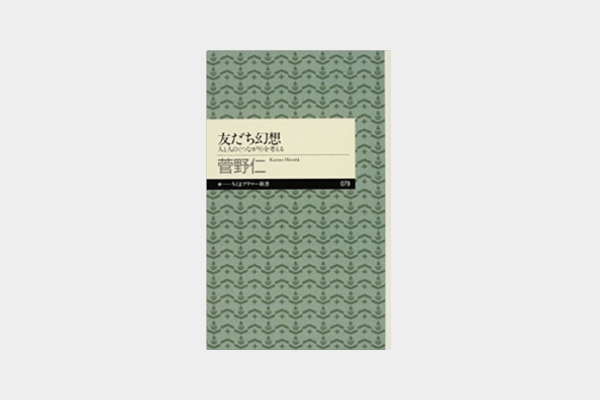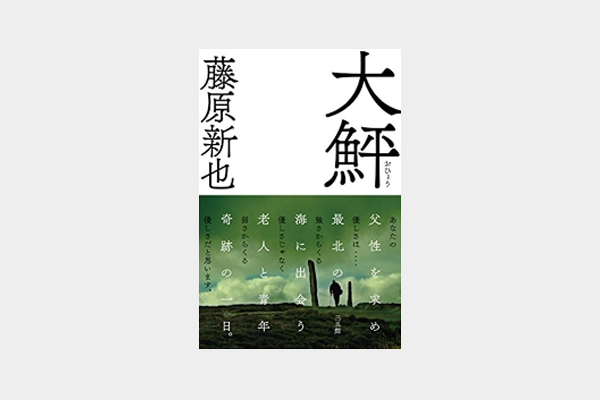映画「君の名は。」「天気の子」などの音楽を手掛けるRADWINPSのボーカル野田洋次郎さん。
19歳でデビューが決まり、そこからミュージシャンとして頂点を目指し駆け上がってきた彼らは、今や若者たちのカリスマ的存在であり、輝かしい成功を収めました。
しかし、野田さんのその成功までの道のりは決して順風満帆なものではなかったそうです。
小学校の頃をアメリカで過ごし、アメリカで3回、日本で1回転校を経験した野田さん。“アメリカ帰りのアイツ”とからかわれるようになり、唯一の気持ちの拠り所である家庭では、父親との...
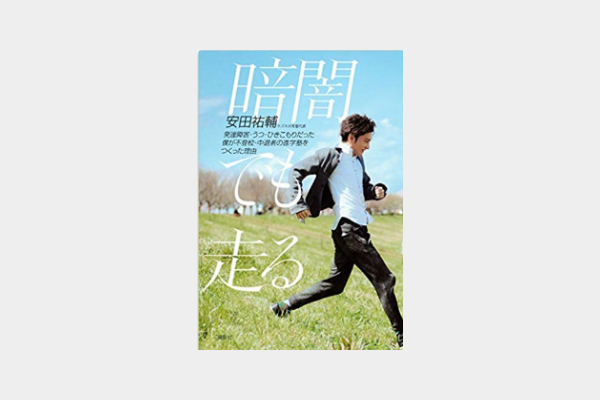
数年前にビリギャルが一念発起して慶應大学に入学したという本が話題になりました。この本もその系統に属する稀有な努力の話だと思います。
著者の安田さんは1983年生まれですから、現在35歳。彼は絵に描いたような崩壊家庭で育ちました。彼の父は浮気性で、次から次へと外に愛人を作り、家にもほとんど帰ってきませんでした。
<父と母の怒鳴り合いや殴り合いの中で、「浮気」や「不倫」といった言葉が飛び交っていた>
父親だけではなく、そのうち母親も家に帰ってこなくなりました。父への腹いせに、母もまた浮気をして、家に寄り付...
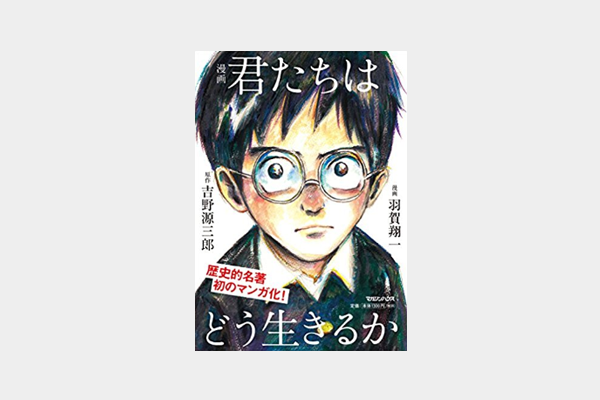
今や新聞に1頁広告が出るくらいですから、とてつもないベストセラーになっているようです。漫画だけで100万部、原作も含めると130万部を越えるというからすごい。私も10代の頃に原作を読んだ記憶がありますが、かなり難解だったという思い出しかありません。
原作者の吉野源三郎さんは明治32年(1899年)生まれの編集者で、岩波書店の雑誌「世界」の初代編集長だった、と本の帯にあります。
物語は比較的単純で、著者の分身と思われる「おじさん」が、主人公である中学生の「コペル君」(彼のお母さんが「おじさん」の姉にあ...
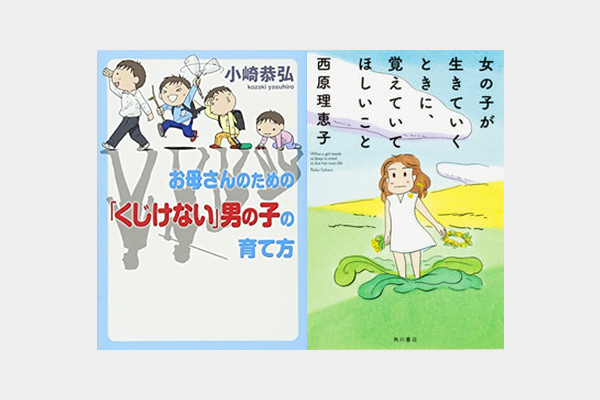
①小崎恭弘『お母さんのための「くじけない」男の子の育て方』
②西原理恵子『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』の2冊を読む
今回はたまたま一緒に読んで興味深かった2冊の本を同時にとりあげることにします。両方とも長いタイトルなので①、②と表記しましょう。
①の小崎さんは大学の教育学部の先生ですが、男性保育士として、施設や保育所に12年間勤務しながら、3人の男の子を育てたという経歴をお持ちです。
②の西原さんは漫画家としても著名で、本の中に「高須先生」への畏敬の念が2~3ヶ所書かれていま...
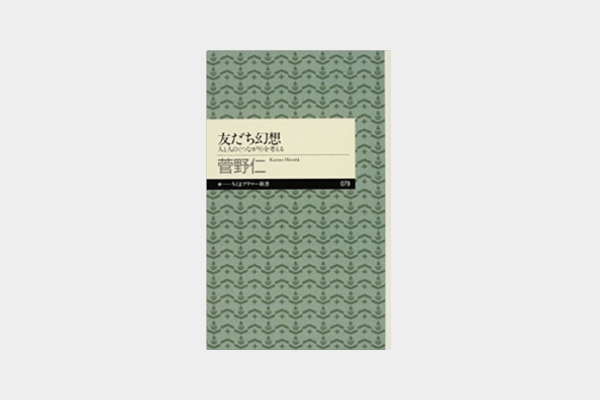
この本は初めに、日本青少年研究所が高校生を対象に行った、「若いうちにぜひやっておきたいことは何ですか」というアンケートの結果から紹介されています。その調査は、日本、アメリカ、中国、韓国の高校生を対象に同時期に実施されたものだそうです。それによると日本の高校生は、「一生つきあえる友人を得たい」とか「いろいろな人と付き合って人間関係を豊かにしておきたい」と答える人がかなり高い割合になったと言います。
そして著者は、同じ日本の高校生が別の問いに対しては、「偉くなりたいとは思わない」「そこそこ生活できればいい」と答...
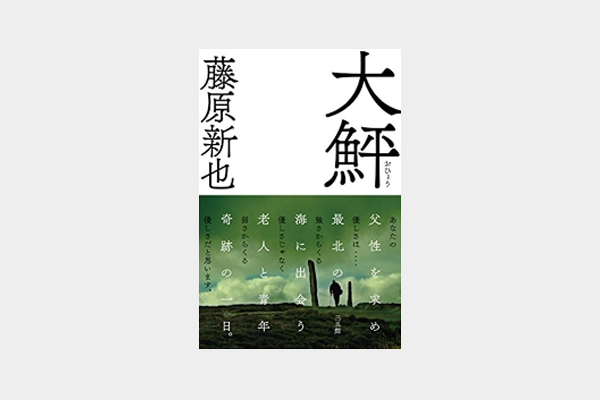
今となっては遠い昔になってしまいましたが、1970年代を中心に、いわゆる「ノンフィクション」と言われる文学ジャンルが大変な隆盛を誇ったことがあります。若い方々にその作者名を尋ねたところ、大半の人が知りませんでしたから、ひょっとするともう歴史上の出来事になってしまっているのかも知れません。
そのノンフィクションというジャンルで、言うところの紀行文学の代表格が今回の藤原新也であり、ゆくゆく取り上げようと思っている沢木耕太郎でした。
この二人に共通しているのは、世界中どこでも全くものおじせずに歩きまわり、その地の...
田中慎弥さんと言っても、知らない方が多いかもしれません。この本の帯にある著者紹介欄によると、その経歴は次のようです。
<1972年山口県生まれ。2005年に「冷たい水の羊」で新潮新人賞を受賞し、作家デビュー。2008年、「蛹」で川端康成文学賞、「切れた鎖」で三島由紀夫賞を受賞。2012年「共喰い」で芥川龍之介賞受賞>
私は芥川賞受賞ということで「共喰い」は読み、映画化された作品も観た記憶があります。
さて、今回の『孤独論』は口述筆記してできあがったものだと「あとがき」にあります。日頃から彼が考えていた...
この本は、著者である稲泉さんが友人や先輩たちにインタビューして、どうして今働いているのか、あるいは働いていないのか、働けないでいるのかを丁寧に聞き取って編集したものです。
稲泉さんの問題意識は明解で、ズバリ次のような文章にはっきり表明されています。
<いま、社会に溶けこめない若者たちや、あえて溶けこまない若者たちが確実に増加している。そうした若者たちは、フリーターや不登校、引きこもりなどと呼ばれ、「問題」とされている。ときにはその現象を「異常」だと言う者もいる。彼らは問題視されながら、社会の異物とし...
平成28年度上半期の芥川賞に決まった村田沙耶香さんの『コンビニ人間』がとても面白かった。この小説が初めて掲載された「文芸春秋」9月号(平成28年)には、選考委員の方々の短い書評が載っていますが、私の感想はそれらのどの批評とも異なっていました。
作者の村田さんは受賞後のインタビューで
<主人公と私は、全く違いますね。私は一から人物を作らないと書けないので、モデルはいないです。>
と語っています。全く新規に造型された人物像だとしますと、そのリアルさには舌を巻くしかありません。ところが、作者は自分自身も長い...
発達障がいをもった類が、日本で一人前のモデルや俳優になっていく過程には、母親の泉さんの献身的なサポートがありました。そして、実は泉さんにも発達障がいがあり、長い間苦しんできた歴史がありました。泉さんのコメントです。
<精神科医と児童心理学者から、私自身が典型的なADHD(注意欠陥多動性障害)であるとの意見が出て、その時は満場一致で「明らかに典型的なADHDだ」とのご意見をいただきました。>
この診断の前後にお会いしたのが、のちに10年以上にわたって類がお世話になる精神科医の高橋先生だったのです。高橋先生...